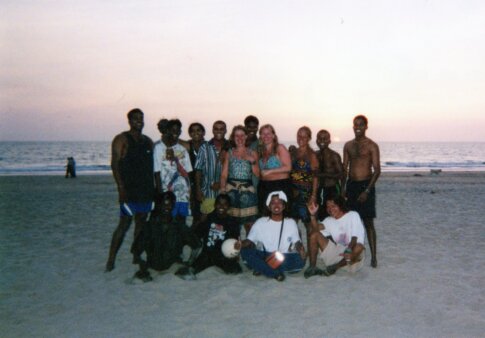こんにちは!keeです。今年もいよいよ始まるマラソンシーズン。世界中のランナーたちも、そして私も過去の自分を超えるために日々、弱い自分と闘い続けています。
『量をこなしていないやつに、質を語る権利はない』本田圭佑の言葉です。
量が大事だとは、私も思います。
でも量だけやっていればいいのか?となるとそうは思いません。量をやった後に質が付いてくるとも思いません。量だけを目指してトレーニングすれば恐らくケガをしてしまうでしょう。
『質を考えながら、量をやる!!』これが成長へのためには必要と私は考えます。
そして今回話すのは、その質の話。
より効果の高いトレーニング方法は日々研究されていますが、ダニエルズのランニング・フォーミュラは1998年からベースは変わらず改良され続けているトレーニング理論の話。第4版!!
ランニングエコノミー(Running Economy)とは、一定の速度で走るために必要な酸素消費量(もしくはエネルギー消費量)の効率を表す指標です。簡単に言えば、同じペースで走ったときに『どれくらい少ないエネルギーで走れるか』というランナーの省エネ性能を示します。
必要な知識なので覚えておいてください。
ダニエルズのランニング基本原則
基本原則1 ランナーはそれぞれ固有の能力を持っている:自分の強みを活かす
基本原則2 常にポジティブなことに目を向ける
基本原則3 好不調があることを見込んでおく:良い日もあれば、悪い日もある
基本原則4 予想外のことに備え、トレーニングには柔軟性をもたせる
基本原則5 中期目標を設定する
基本原則6 目の前の課題に集中する
基本原則7 レースのミスはたいてい前半に起きる
基本原則8 トレーニングはやりがいを感じるものであるべき
基本原則9 質のよい食事と睡眠をとる
基本原則10 病気にかかっているとき、ケガをしているときはトレーニングをしない
基本原則11 慢性的に身体の不調があったら医師の診察を受ける
基本原則12 うまく走れた、いいレースができた、というとき、それはけっしてまぐれではない

トレーニングの原理
まずはトレーニングが身体にどう影響するか理解しておきたい。また、トレーニングのタイプが異なればストレスを受ける身体システムも異なる、という事実もわかっておいたほうがいい。身体はある特定のストレスを受けるたびに、さまざまな部位で直ちに反応する。そして、同じストレスを受けるたびに同じように反応するが、時が経つと、同じストレスの繰り返しに対して違う反応が起きるようになる。これが身体が強くなった、ということである。
人間の身体は、さまざまなストレスに対して非常にうまく適応するが、ストレスによっては、完全に適応するのに長い時間がかかることもある。トレーニング量・強度・頻度が身体にとって過剰なストレスとならないよう、トレーニングの各原理を理解し、活用できるようになることが重要である。
オーバーストレス
ストレスが増えればその分適応も増えるが、別の原理が働く可能性もある。それは『オーバーストレス』の原理だ。ある部位に過剰なストレスが加わると、その部位がそれ以上強くならなくなることもある。むしろ弱くなったり、完全に故障したりするかもしれない。
ならば、身体はストレスに対して反応しているあいだの、どこで強くなっているのだろうか。
それは、一連のストレスの合間の『回復期』である。
つまり休養している時間に身体の強化は起きるのである。
休養と回復はトレーニングプログラムに欠かせない大切な要素である。それはトレーニングをサボることではない。時と場合によっては、走るよりも休みにした方がいいこともあるし、きつい練習よりもストレスの小さい練習をした方が身になることもある。
もしも練習の候補が2つあって迷うときは、ストレスの『小さい方』を選ぶこと。
この考え方はぜひ参考にしてほしい。
トレーニングに対する反応
新たなトレーニングストレスによる効果は、時間が経つと薄れていく。そして何週間も同じトレーニングを続けているだけでは、体力レベルの向上も頭打ちになる。
トレーニングから効果を得て、新たな体力レベルに到達するには6~8週間かかるが、それからさらに向上するには、再度トレーニングストレスを増やす必要があるのだ。
ランニングの場合、トレーニングストレスを増やすには変えられる要素が4つある。
- 量を増やす:距離を延ばす(他の要素は変えない)
- 強度を上げる:ペースを上げる(距離は延ばさない)
- リカバリーを短くする:間の休息を10分から5分など(量を強度は変えない)
- 頻度を増やす:週3回から週4回または5回(量・強度・リカバリーは変えない)
4つの可変要素のうち、量・強度・頻度の3つはどんな練習にも必ず存在する。
そして4つの要素のうち、2つ以上の要素を変えるのはよくない。
通常はこの4つの要素のうちどれを増やしても、体力は新たなレベルへと向上する。
個人の限界
体力は、トレーニングストレスを増やせば向上し続けるとは限らない。
ある一定のレベルを超えると別のトレーニング原理が働くのだ。
それは誰でも超えられない絶対的な限界があるわけではなく、個人には、それぞれにシーズナル・リミットがあるという意味だ。
『シーズナル・リミット』とは、ある一定期間のライフスタイルによってもたらされる限界のことである。職場や家庭などで果たすべき務めは人生のステージでさまざまに変わる。それによってトレーニングは難しくなったり、また楽になったりするものだ。
いずれにせよ、絶対に避けるべきはオーバートレーニングである。
トレーニングの強度は、現時点での体力で決めるべきだが、その最良のものさしは、レースパフォーマンスである。
維持の原理
あるレベルの体力を新たに獲得するよりも、維持するほうがやさしいというトレーニング原理。
1マイルのレースを5分で走るためのトレーニングを続け、達成できたとする。そうすれば、再度5分で走ることは最初ほど大変ではない。
生理学的に見れば、これは体力レベルが一段階アップしたということでもある。心臓は強くなり、活動筋に酸素を運ぶ毛細血管が増える。そして、活動筋の細胞自体も、燃料をより効率的にエネルギーに変えられるように変化しているのだ。
レース前のテーパリングを見てもわかる。テーパリングを行い、トレーニングストレスをいくらか落とせば、レースではよりよい結果につながる。トレーニングストレスを減らしている間に、体力を維持できるだけでなく、向上させることもできるわけだ。
この事実は、維持の原理の確かな証である。
トレーニング原理を応用したプログラムの作成
トレーニングの原理を十分に理解していれば、オーバートレーニングのリスクを最小限に抑えながら、最大限の効果をトレーニングから引き出すことができる。
もっとも大きな効果は、もっともきついトレーニングではなく、もっとも少ないトレーニングで狙う。
これを忘れないでほしい。
トレーニングストレスを増やすというときは、まず6~8週間、トレーニングストレスを一定に保つこと。変更を加えるのはそのあとである。
1週間ごと、あるいは1回ごとにトレーニングの質を上げようとするのは間違いだ。
前回より少しでも早く走ろうとするより、いつもの練習がだいぶ楽になってきたという状態を目指そう。
最後に足の運び方の説明をして今回は終わりたい。

ストライド頻度(ピッチ)
オリンピックのマラソンで金メダルを獲得したあるランナーについて、実際にテストをしたことがある。このランナーが1マイル7分(1㎞4分22秒)ペースで走ったとき、ピッチは1分間に184回であった。
そこでペースを上げさせると1マイル6分(1㎞3分45秒)では186回、1マイル5分(1㎞3分8秒)では190回となった。
ペースの上昇率がピッチの上昇率をはるかにはるかに上回ったのだ。
ランナーにとってもっとも快適と思われる特定のリズムが存在すること、そして、快適に感じるリズムは別の種目でストライド長を変え、ベースを上げたとしてもほとんど変わらないことがこの結果からはっきりとわかる。
1分間180回ピッチ
ピッチは1分間180回程度を目指すよう、強く推奨されているが、その理由の一つは、接地の衝撃をできるだけ小さくするためである。脚の回転が遅くなるほど滞空時間が長くなる。
そして滞空時間が長くなるほど身体は高く持ち上がり、身体が高く持ち上がるほど次の接地時の衝撃は大きくなる。
これを忘れないことだ。
実際にちょっとしたケガの多くは接地の衝撃を受けたときに起きる。
では、どうしたら接地の衝撃を小さくすることができるのだろうか。
簡単に言うと、一歩一歩バウンドせずに、まるで地面を転がるようなつもりで走る。
足を自分の身体の前に置こうとしないこと。こうするとたいていはブレーキをかける動きになり、次の一歩の衝撃が増す。膝を痛めやすいランナーは要注意。接地はそれよりも後ろ寄り、重心をめがけて足を置くようにしよう。
そうすれば、身体は両足の上方で浮く(転がる)ようになる。
まとめると、
『接地は1分間180回を心がけ、なるべく力は使わずに地面を転がる感覚をつかむ』
そうすればランニングは今よりもずっと楽しくなり、ケガも減るはずだ。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。